指定難病3『脊髄性筋萎縮症(Spinal Muscular Atrophy:SMA)』とは?

今回は、指定難病3。『脊髄性筋萎縮症(Spinal Muscular Atrophy:SMA)』について説明したいと思います。
脊髄性筋萎縮症の説明
脊髄性筋萎縮症(SMA)は、脊髄の運動ニューロン(筋肉を動かす神経細胞)が少しずつ機能を失っていく、進行性の希少な神経‐筋の病気です。
手足の筋肉が弱くなったり、立ったり歩いたりするのが難しくなったりします。
発症年齢と重症度によってI型~IV型に分類され、小児期に発症するものが多いですが、成人発症例もあります(指定難病の条件に合致しています)。
日本での有病率は人口10万人あたり1~2人程度とされており、発症すると長期の療養・支援が必要となることがあります。
脊髄性筋萎縮症を分かりやすく説明すると
この病気をもっと簡単に言うと、「体を動かすための神経の“指令線”がだんだん細く弱くなってしまい、その結果、手足や体幹の筋肉がうまく動かせなくなってくる病気」です。
例えば走ったりジャンプしたりすることはもちろん、立ったり座ったり、歩いたり、時には腕を上げることさえも、以前より“重たく感じる”ようになることがあります。
発症年齢や重さによってタイプが違い、例えば赤ちゃんのうちから重く進行するタイプもあれば、成人になってからゆっくり出るタイプもあります。
原因は遺伝子(SMN1遺伝子)の変化によるもので、「なぜ起きるか完全には解明されていません」が、研究が進んでいます。
残念ながら「治せる薬」が完全に出そろっているわけではありませんが、最近は“進行を遅らせる”“生活を支える”治療が出てきており、早めに専門医と相談してケアを始めることで、暮らしの質を守ることができます。
脊髄性筋萎縮症の症状
- 手足の力が弱くなってきて、歩く・立つ・走るが難しくなる。
- 筋肉が細く萎えていく(筋萎縮)・筋緊張が低くなる(筋肉が“ゆるく”感じる)
- 種類によっては、呼吸筋や飲み込み(嚥下)に関わる筋肉も影響を受け、呼吸困難・誤嚥・栄養管理が必要になることも。
- 成人型(IV型)では進行がゆるやかで、歩行期間が長いケースもあります。
現在分かっている原因と研究の動き
この病気の主な原因は、SMN1遺伝子の欠失や変異によってSMN(survival motor neuron)タンパク質が十分につくられなくなることです。
SMNタンパク質が減ることで、運動ニューロンが徐々にダメージを受け、筋肉を動かす指令が滞るようになります。
ほとんどの場合、常染色体劣性(両親から異常遺伝子を受け継ぐ)遺伝形式です。
発症年齢・重症度は、持っているSMN2遺伝子のコピー数などによって変わるとされています。
脊髄性筋萎縮症の治療法
根本的に「完全に治る」治療法がすべての型で確立されているわけではありません。
とはいえ、近年では下記のような治療・ケアが進んでいます。
- 遺伝子治療・薬物療法:SMNタンパク質量を増やす治療薬が承認・実用化されつつあります。
- リハビリテーション:筋力低下や関節拘縮(体を動かしづらくすること)を防ぐ理学療法・作業療法。
- 補助具・呼吸ケア・栄養ケア:歩行補助、呼吸器支援、嚥下機能のサポートなど。 早期発見・早期治療開始が、重症化を抑える鍵となります。
脊髄性筋萎縮症の患者数
日本国内では、乳児期~小児期に発症するSMAの発症頻度は10万人あたり1~2人程度と報告されています。
また、国内患者数については「1,000人程度」「受給者証所持者数が955人(2025年時点)程度」との報告があります。
家族・介護職が意識したい支援のポイント

- 転倒・腰掛けなど動作補助の必要性が高く、自宅の手すり設置、滑り止め床、移動補助機具の導入が効果的です。
- 呼吸・嚥下機能低下が起こる可能性があるため、誤嚥防止や体位管理、栄養補助・吸引ケア・呼吸リハビリも重要なケア項目です。
- 筋力低下が進むと関節が動きにくくなる(拘縮)ため、関節可動域維持・ストレッチ・体位変換・理学療法を定期的に実施しましょう。
- ご家族・介護者も長期的ケアとなるため、心理的支援・地域サービス・難病相談支援センターの活用を早めに検討してください。
- 補助具(車いす・立位保持装置など)や福祉用具・住宅改修の助成制度を活用することで、介護負担軽減につながります。
まとめ|脊髄性筋萎縮症を理解して前向きに支えるために
- 運動ニューロンが障害されることで、筋力低下・筋萎縮が生じる神経‐筋疾患です。
- 発症年齢や重症度によりI型~IV型に分類され、10万人あたり1~2人とまれな病気です。
- SMN1遺伝子の異常が原因で、根本治療はまだ完全には確立されていませんが、遺伝子治療やケアが進展しています。
- 転倒・呼吸・嚥下・拘縮など多面的な介護支援が必要で、早期のケアが生活の質維持に重要です。
- 遺伝性疾患であるため、家族や保因者の存在・検査・遺伝カウンセリング等も考慮すべきです。
参考引用)公益財団法人、難病医学研究財団『難病情報センター』ホームページより。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。
次の記事はこちらです。👇
https://hajimetenokaigo.com/nanbyo-4-pls/
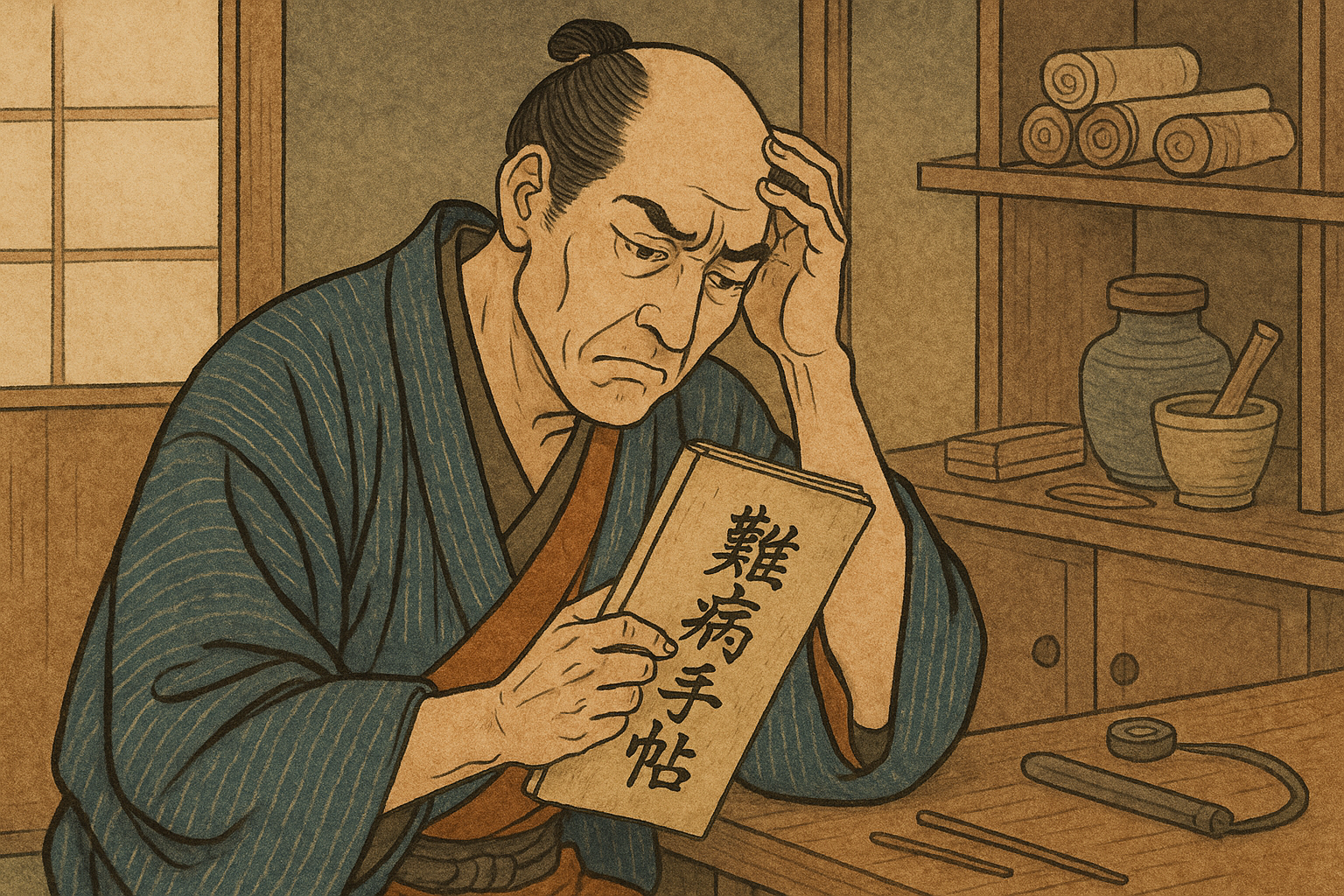
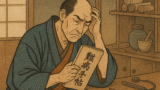
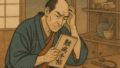
コメント