指定難病4『原発性側索硬化症(Primary Lateral Sclerosis:PLS)』とは?

今回は、指定難病4。『原発性側索硬化症(Primary Lateral Sclerosis:PLS)』について説明いたします。
原発性側索硬化症の説明
45歳を過ぎて、「足がつっぱる」「階段がしんどい」といった症状が現れたら、それは神経の異変のサインかもしれません。
原発性側索硬化症(PLS)は、脳から脊髄へ体を動かす命令を送る「上位運動ニューロン」が徐々に障害されることによって、筋肉の動きがぎこちなくなったり、つっぱったりする神経変性疾患です。
進行は比較的ゆっくりしており、感覚神経や内臓機能が保たれる特徴があります。
原因は明らかではなく、現在も診断・治療の研究が進められている希少な病気です。
原発性側索硬化症の分かりやすい説明
想像してみてください、体を動かすスイッチを入れるための「電線」が少しずつ錆びてきて、信号が遅くなったり伝わりにくくなったりするような状態。
それがこの病気です。
具体的には、例えば歩くときに足が「ガチッ」と固まった感じがする、階段を降りるときにつまづきやすい、それから腕を上げるときに重たく感じる――そんな“違和感”が出てきます。
感覚や痛みはあまり変わらない点がポイントで、むしろ「自分の意志では動かせない」「体が思った通りに動かない」というもどかしさが強く出ます。
残念ながら、この病気を完全に治す薬は今のところ確立していません。
でも、日常生活の質を守るためには、早めに神経内科を受診し、リハビリや補助器具など“出来ること”を始めることが大切です。
原発性側索硬化症の症状
- 典型的には**下肢のつっぱり(痙性)**から始まり、足の動きがぎこちなくなります。
- その後、上肢にもつっぱり感や力が入りにくいといった症状が出ることがあります。
- さらに進むと、**話しにくい(構音障害)・飲み込みにくい(嚥下障害)**が現れる場合があります。
- 感覚神経や視覚・聴覚・内臓機能は比較的保たれるため、「動きにくさ」に焦点が当たる疾患です。
現在わかっている原因と研究の動き
現時点では、原発性側索硬化症の原因は明確には解明されていません。
若年型の一部には遺伝的変異が報告されているものの、一般的には「なぜ起こるか」が不明で、研究対象となっています。
原発性側索硬化症の治療法
この病気を根本から「治す」治療法は現時点では確立されていません。
しかしながら、以下のような対策・ケアによって症状の進行を抑えたり、生活の質(QOL)を維持したりする取り組みが行われています。
- リハビリテーション(ストレッチ・動作訓練)による筋緊張の調整
- 補助具・杖・歩行器・環境整備による転倒予防
- 構音・嚥下リハビリや言語療法の導入
- 痙性を和らげる薬物治療(痙攣やこわばりに対する)
原発性側索硬化症の患者数
日本において、この病気の有病率は人口10万人あたり約0.1人程度と報告されています。
患者数自体は非常に少ない「希少疾患」に位置づけられています。
家族・介護職が意識したい支援のポイント

- 歩行・移動がぎこちなくなるため、床面の段差解消・手すり設置・滑りにくい床材といった住宅内環境の整備が重要です。
- 足や腕の筋肉が“つっぱる”ことで転倒リスクが高まるため、**転倒予防策(夜間の照明確保・移動補助器具)**を検討してください。
- 話しにくさ・飲み込みにくさが出た場合には、言語療法・嚥下リハビリ・食事姿勢の工夫が早めの段階から役立ちます。
- 感覚器や内臓機能は比較的保たれるものの、心理的な不安・動きづらさ・将来への備えを家族・ケア職員ともに共有し、ケアプランに組み込むことが望ましいです。
- 補助具・福祉用具・訪問リハビリ・難病相談支援センターの活用も、介護負担軽減に繋がります。
まとめ|原発性側索硬化症を理解して前向きに支えるために
- 上位運動ニューロン(脳からの運動指令を担う神経)が主に障害される神経変性疾患です。
- 発症頻度は人口10万人あたり約0.1人と非常に稀な病気です。
- 根本的な治療法は確立されていませんが、リハビリや補助具・環境整備などの支援で生活の質を向上させることが可能です。
- 下肢のつっぱり・歩行障害・話しにくさ・飲み込みにくさが代表的な症状です。
- 介護・支援の観点では、転倒予防・移動補助・嚥下支援・住環境整備がカギとなります。
参考引用)公益財団法人、難病医学研究財団『難病情報センター』ホームページより。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。
次の記事はこちらです。👇
https://hajimetenokaigo.com/nanbyo-5-psp/
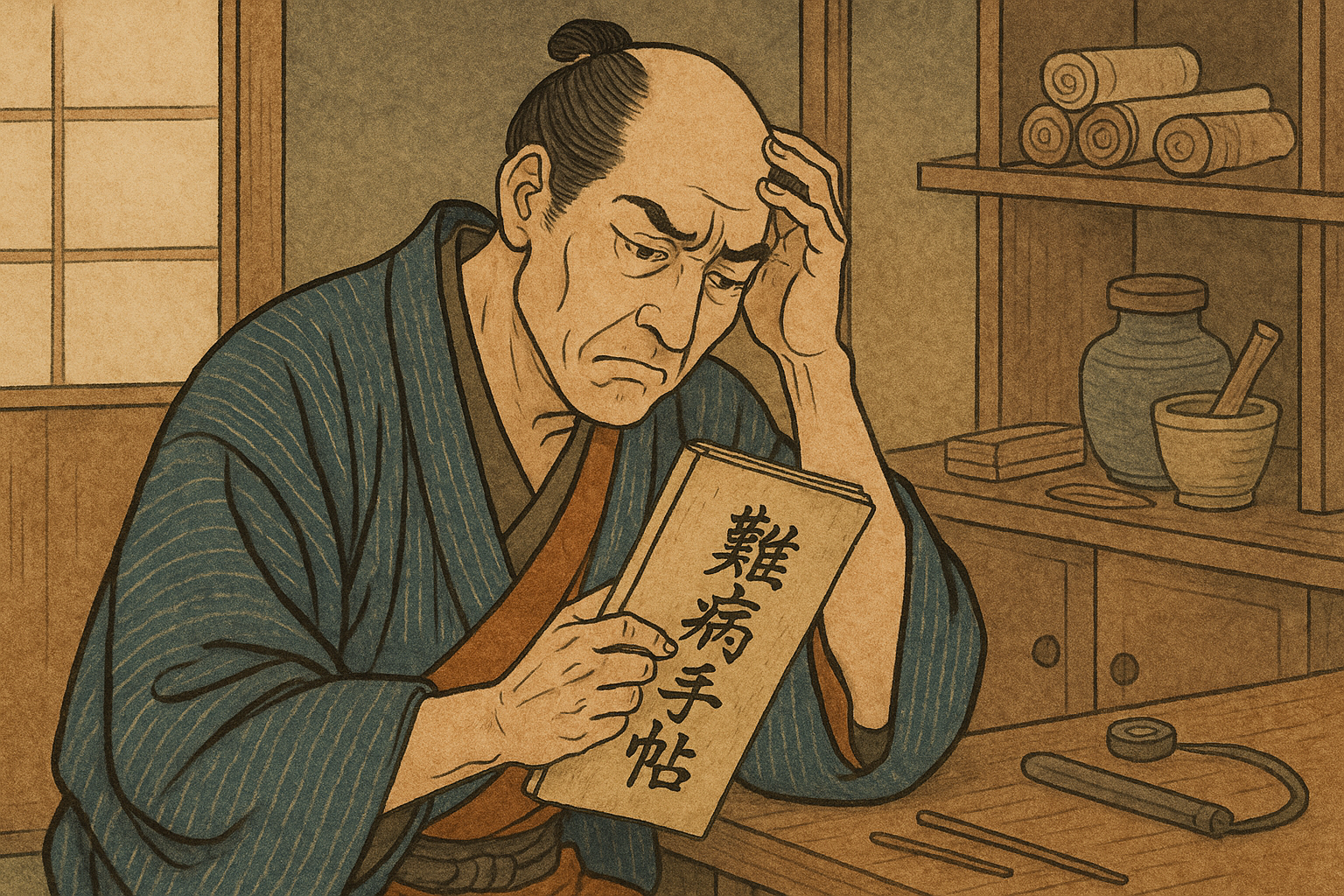
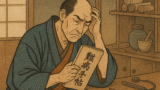
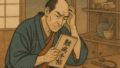
コメント