
今回は、指定難病2、『筋萎縮性側索硬化症(ALS)』について説明したいと思います。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)とは?分かりやすく説明します。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、運動ニューロン(運動を司る神経細胞)が徐々に機能を失い、筋肉が萎縮していく神経変性疾患です。
進行性であり、現在のところ根本的な治療法は確立されていません。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)を分かりやすく説明すると
運動をつかさどる神経の病気で、脳からの「手足を動かせ」という命令が伝わらなくなり、筋肉が痩せていく病気です。
身体が動かし難くなっていく一方で、身体の感覚や視力や聴力、内臓機能などは保たれるのが特徴です。

痛みや痒みは残るのに、身体が動かせないので、対応が出来なくなるのが辛い病気だと思います。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の症状
初期症状としては、手足の筋力低下(手がうまく動かせない、歩きにくい)、つまずきやすくなる、話しづらい、飲み込みにくい、などが出てきます。
進行してくると、筋力低下が全身に広がり、歩行困難になり、嚥下障害が進行し、経管栄養(胃ろうなど)が必要になる、呼吸筋が障害され、人工呼吸器が必要になる、などの症状があらわれます。
現在わかっている原因と研究の動き
原因は解明されていませんが、
・神経の老化
・興奮性アミノ酸の代謝異常
・酸化ストレス
・タンパク質の分解障害
・ミトコンドリアの機能異常
など、さまざまな説があります。
遺伝による発症は、家族性ASLと呼ばれていて、全体の10%程度です。
多くの場合は遺伝しません。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療法
進行を遅らせる薬として、リルゾール(グルタミン酸の過剰を抑制し、進行を遅らせる)、あるいはエダラボン(抗酸化作用を持ち、病気の進行を抑える可能性がある)が使われます。
体重が減っている場合には、高カロリー栄養療法が大切である事が分かっています。
対症療法として、
筋肉や関節の痛みに対しては、毎日のリハビリを早期から始める事が大切です。
嚥下障害に対しては、食事の形態やトロミ剤の使用、高カロリー食、胃ろうの造設などをおこなっていきます。
呼吸障害に対しては、非侵襲的人工呼吸器や気管切開+人工呼吸器、痰の吸引なども必要になっていきます。
コミュニケーション支援としては、初期には筆談や文字盤、タブレットを利用し、進行時には視線入力装置や音声合成アプリを使用することもあります。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者数
全国に約10,000人の患者さんがいると言われています。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症年齢は中年以降のどの年齢の人でもかかる事がありますが、特に60〜70歳に多く見られます。
性別で見ると、男性の方が女性より、1.3〜1.5倍多く見られます。
1年間で新たにこの病気にかかる人は、人口10万人あたり、平均2.2人となっています。
家族・介護職が意識したい支援のポイント

身体は動かしにくくなっていきますが、身体の感覚は保たれるので、痛みや痒みなどの苦痛は感じるが、それに対して自分で動いて対処する事ができない、という状況になっていきます。
この点を理解して、介護にあたることは、非常に大切だと思います。
ALSでは、体重が減ると病状が悪化することが知られており、体重を維持することは大切だと考えられています。
まとめ|筋萎縮性側索硬化症(ALS)を理解して前向きに支えるために
- 筋肉が萎縮していく病気
- 身体の感覚や視力・聴力、内臓機能などは保たれる
- 神経変性疾患
- 根本的な原因は分かっていないので、予防や根治は難しい。
- 進行を遅らせる薬はある
- 体重が減ると病状が悪化する
参考引用)公益財団法人、難病医学研究財団『難病情報センター』ホームページより。
それでは今回はこの辺で失礼いたします。
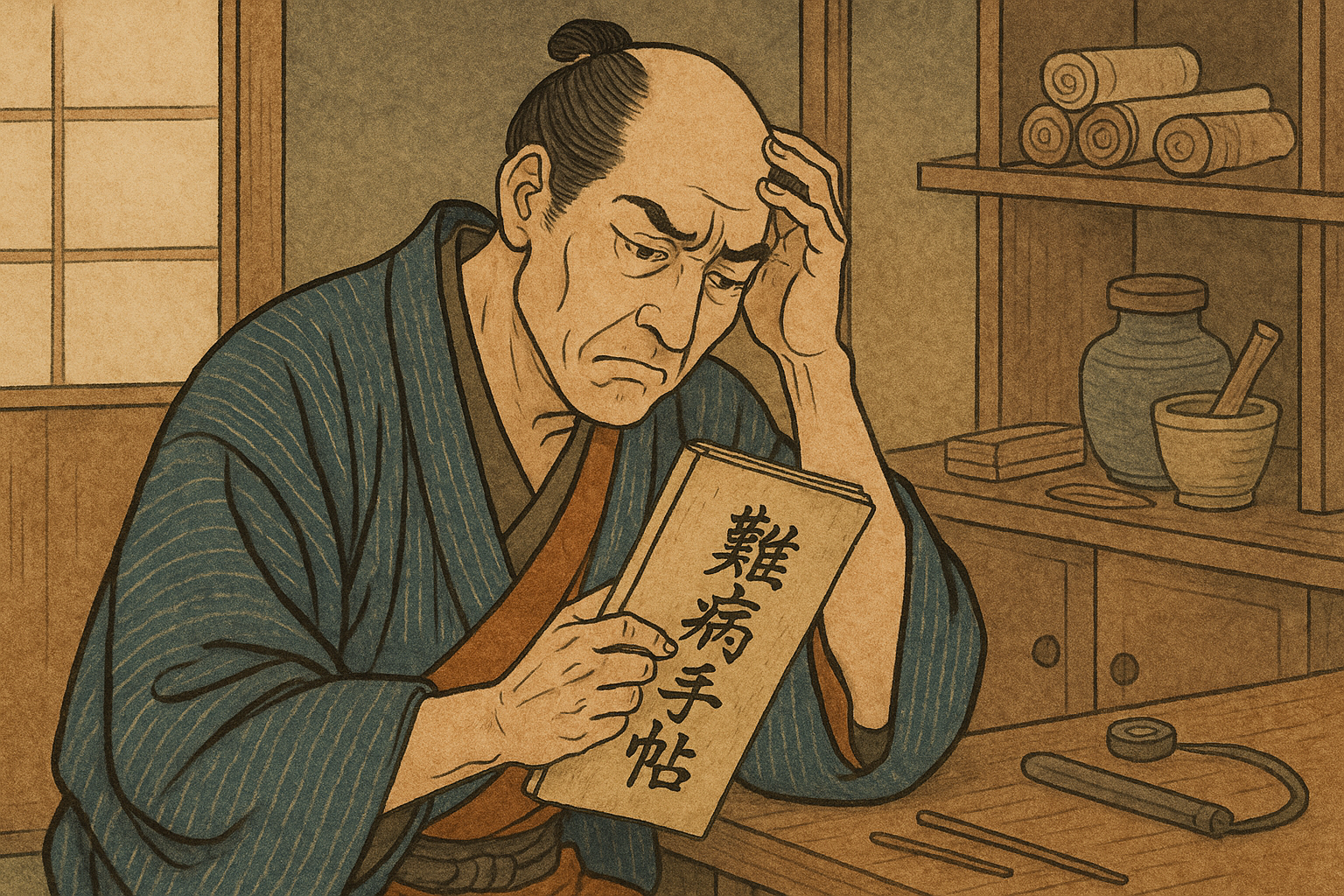
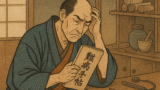


コメント